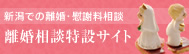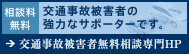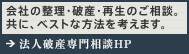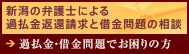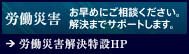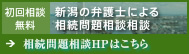最新情報
事務所からの最新情報や法律に関する情報をご紹介します。
公訴時効と免訴判決(弁護士:谷尻 和宣)
2022年6月20日
コラム
最高裁判所は、2022年6月9日、かつて代表取締役を務めていた会社から、現任の取締役と共謀し、預金を不正に流出させたとして業務上横領罪に問われた元社長について、公訴時効の完成を認めたうえで、実刑判決とした第二審高裁判決を破棄しました。
これにより、免訴判決を言い渡した第一審判決が確定します。
この判例は、刑法や刑事訴訟法上の論点が多数含まれておりとても興味深いのですが、詳細は省略し、この機会に公訴時効や免訴といった制度について紹介したいと思います。
公訴時効とは
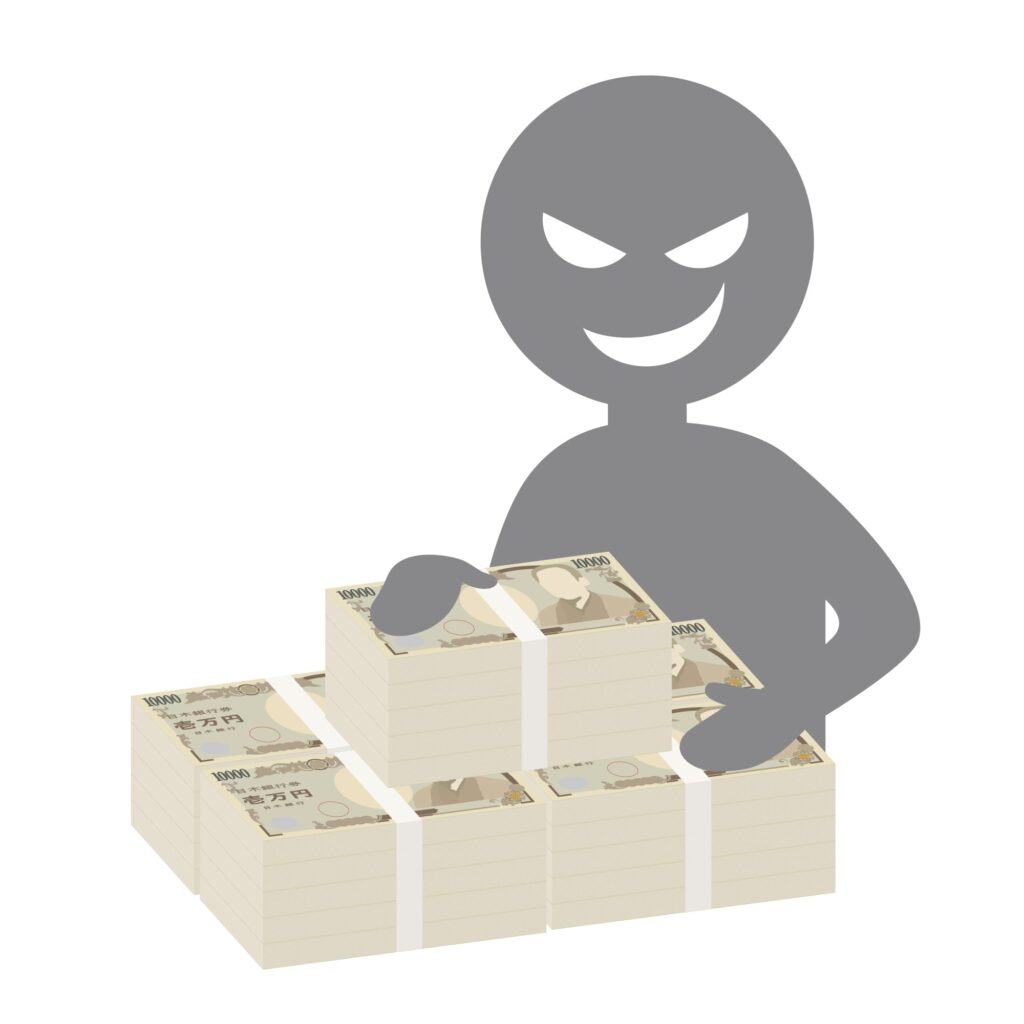
公訴時効とは、一定の期間が経過することにより、検察官が公訴を提起すること(起訴)ができなくなるという制度です。
起訴されないということは裁判にもかけられませんので、たとえ犯人が真実罪を犯していたとしてももはや処罰されなくなるのです。
時間が経過したからといって犯人が処罰されなくなるのは、いわば「逃げ得」にようであり、何とも不合理な制度にも思えます。
どうして公訴時効の制度が存在するのでしょうか。
なぜ公訴時効があるのか
公訴時効の根拠としては、①時間が経過することで、犯罪の社会的な影響が薄れ、犯人を処罰する必要性がなくなるためである、とか、②時間の経過とともに証拠が失われていくから、公正な裁判の実現が困難になるためであるなどと説明されることが多いようです。
しかし、重大な犯罪場合、社会的な影響はそうやすやすと薄れるものではないと思われます。
一方で、刑事裁判は証拠に基づいて行うものですから、犯人にとって有利か不利かを問わず、証拠が失われることは、裁判を誤らせるおそれがあります。
したがって、私個人としては、②の考え方がしっくりくるのではないかと思います。
公訴時効の期間は、刑の重さによって異なりますが、平成22年に刑事訴訟法が改正され、人を死亡させた罪で死刑に当たるものについては公訴時効が廃止されました。
免訴判決とは
通常考えにくいのですが、公訴時効が完成しているにもかかわらず公訴が提起された場合は、免訴判決が言い渡されます。
免訴判決とはあまり聞きなれない用語ですが、どのようなものなのでしょうか。
これについても様々な説明がなされますが、端的に言うと、国に刑罰権がないということを宣言する判決と考えるのが分かりやすいと思います。
公訴時効の場合で言うと、検察官が公訴を提起することができなくなった以上、もはや国が裁判で犯人を処罰することはできない、すなわち国に刑罰権はないということになるでしょう。
今回の判決について
今回の事案では、元社長には業務上横領罪(10年以下の懲役)が成立しますが、退任した後で「業務上」に当たらないため、科される罪は横領罪の限度となります(5年以下の懲役)。
そうすると、公訴時効期間について、成立する業務上横領罪の刑を基準とすべきか、それとも罪を科される横領罪の刑を基準とすべきなのが問題になりました。
最高裁判所は、犯人を処罰する必要性は科される刑に反映されていると言えるから、科される刑を基準とすべきだと判断し、今回の事案では横領罪を基準になるとしました。
そうすると、今回の元社長についての公訴時効の期間は5年となり、犯罪行為を行った時(平成24年7月)から公訴提起(令和元年5月)まで7年近くが経過していることから、公訴時効が完成していることになります。
その結果、元社長は免訴を言い渡されるという結果になるわけです。